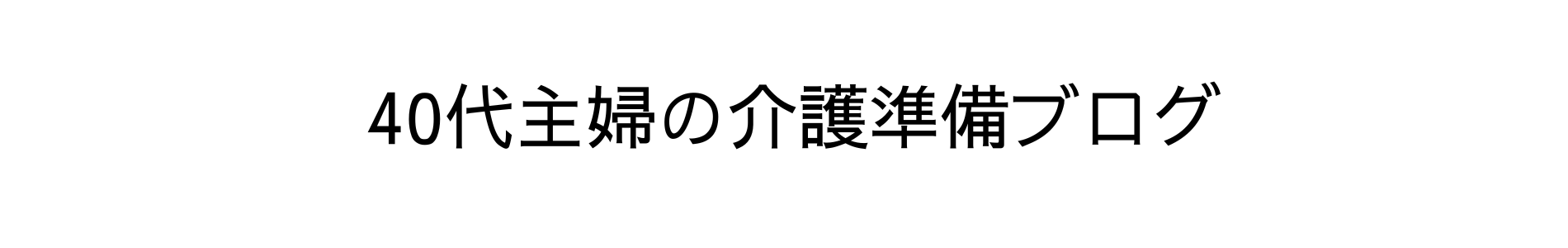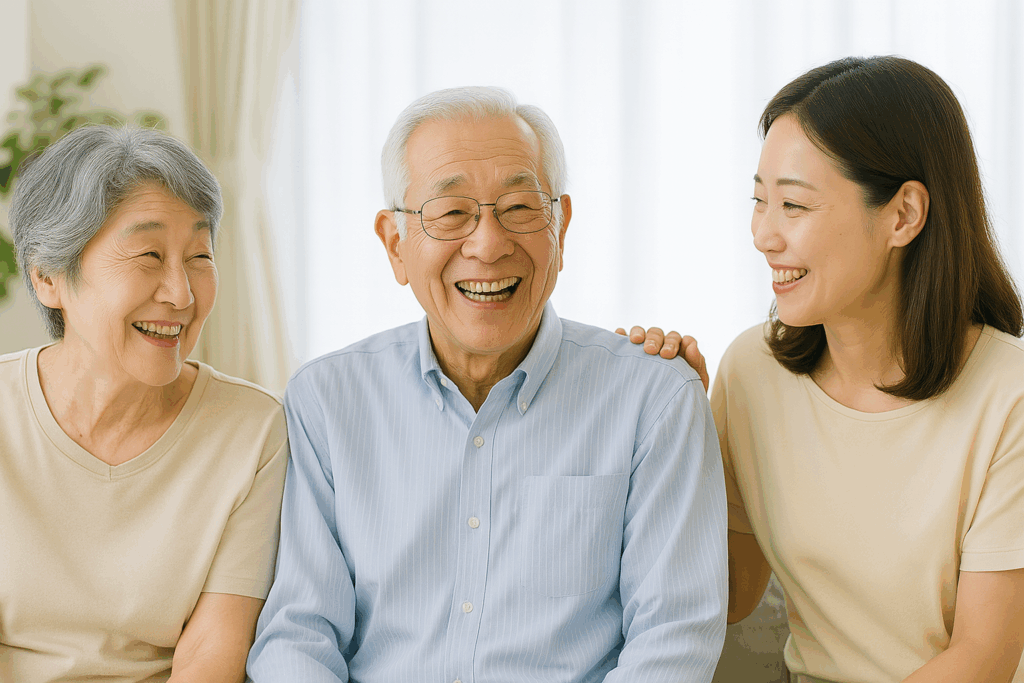
「お母さん、エアコンつけてる?」
「え?まだ大丈夫よ、扇風機で平気だから」
高齢の親にそう返されて、ヒヤッとしたことはありませんか?私の父はここ2年連続で熱中症で意識がなくなり救急車にお世話になっています。なので毎年夏がくると父が心配でちょくちょく実家に連絡してるくらいです。みなさんはいかがでしょうか?
年々暑さが厳しくなる中、高齢者の熱中症リスクは確実に上がっています。
特に室内での熱中症は自覚しにくく、気づいたときには重症化していることも…。
今回は、離れて暮らす親を熱中症から守るためにできる「グッズ」と「声かけ」の工夫を、実例とともにご紹介します。
熱中症は「気づき」と「備え」が命を守る
高齢の親を熱中症から守るには、
- 日常の声かけ習慣
- 使いやすい熱中症対策グッズ
この2つをセットで取り入れることがカギです。
「エアコンは冷えすぎる」「のどが渇いていない」と思いがちな親世代に対し、“無理なく受け入れてもらえる”工夫が必要になります。
なぜ高齢者は熱中症になりやすいの?
高齢者は、以下のような理由から熱中症のリスクが高まります。
- 暑さやのどの渇きを感じにくくなる
- エアコンを「体に悪い」と思い込みがち
- 室内にいても油断してしまう
- 持病や薬の影響で体温調節がしにくい
また、以前母に「エアコンつけてる?」と聞いたところ、 「電気代がもったいないから我慢してる」と言われてびっくりした経験があります。
電気代より健康の方が大事と何度も伝えましたが、 そのとき気づいたのは「本人に悪気があるわけじゃない」ということ。 だからこそ、習慣づけと環境づくりのサポートが必要なのです。
親の熱中症を防ぐためにできること
① 声かけの習慣化(でもうるさくない工夫)
📌 こんな言い方が効果的
- 「今日は暑いから、冷たい麦茶でも飲んでね」
- 「お部屋の温度、ちょっと高めじゃない?涼しくしてね」
- 「うちもエアコンずっとつけてるよ~」
✅ ポイント: 「心配してる」より「共感してる」トーンで話すと、受け入れてもらいやすくなります。
② おすすめの熱中症対策グッズ
🛒 高齢者向け・あると安心なグッズ例
●【冷感タオル・スカーフ】首に巻いて熱を逃がすタイプ
●【温湿度計】室温と湿度がひと目でわかる(エアコン調整の目安に)
●【タイムマーカー付き水筒】飲み忘れや水分補給を促す
✅ ワンポイント: 「これ、便利そうだったから送るね」とさりげなくプレゼントにするのもおすすめですね。
③ 室温の管理を「見える化」する
「暑い」と感じたときにはすでに遅いこともあります。
👀 見える化の工夫
- 温湿度計をリビングと寝室に設置する
- 28度以上・60%以上になったら「エアコンON」のルールを伝える
- 「暑さ指数(WBGT)」を表示するタイプもおすすめ
✅ 実際の体験談: 我が家では母が「今日は寒いくらいよ」と言っていたのに、実際の室温が29度で驚いたことがあります。 温湿度計を送ったら、 「見たらちゃんと調整するようになった」と言ってくれました。
④ 外出時の工夫と声かけ
👒 外出前の一言
- 「帽子かぶっていってね」
- 「日陰で休みながら歩いてね」
🧴 必携アイテム
- 日傘・帽子
- 携帯用扇風機
- ペットボトルに入れた冷たい飲料水
✅ ちょっとした気づかい: 外出予定があると聞いたら「何時ごろ帰る?」「あとでLINEしてね」と伝えておくと安心感もアップ。
⑤ エアコンを上手に使える環境を整える
🛠 工夫できること
- リモコンの設定方法を紙に書いて貼っておく
- エアコンが古い場合は節電モデルに買い替え提案
- フィルター掃除も代わりにやってあげると喜ばれる
✅ ワンポイント: 「体に悪い」は昔の常識。今は「体にやさしいのがエアコン」と伝えてあげましょう。
まとめ
高齢の親にとって「暑さ」は命に関わる大敵です。
でも、うるさく言わなくても、
- 見える化
- 声かけの工夫
- 便利なグッズの活用
で、“やさしく、自然に”熱中症予防をすすめることは可能です。
「毎年同じことを言っている気がする…」 「ちゃんと伝わっているかな?」
そんな不安を感じる方こそ、 この記事の中の小さなヒントを試してみてください。
最後に:今日からできる3つの一歩
- 温湿度計や冷感グッズを1つだけでも用意してみる
- 「暑いから麦茶飲んでね」とLINEしてみる
- エアコンの使い方や掃除を一緒に確認する
親にとっては「暑さに耐えること」より「誰かに気にかけてもらっていること」のほうが心強いのです。
あなたのその一歩が、親の健康を守る“やさしい見守り”になりますように。