「親はまだ元気だけど…介護になったらどれくらいお金がかかるの?」 そんな疑問を持ち始めた40代主婦のあなたへ。私もそんな1人です。自分の将来も不安だけど、近いうちにくる親の介護費も気になりますよね。まだ親が元気なうちに相談しておけばあとあと楽に準備もできるはずです。
実は、介護はある日突然始まり、そのとき“何の準備もしていなかった”という声がとても多いのです。 この記事では、介護費用の平均額と、40代の今からできる備えをわかりやすく解説します!
親の介護費用いくら?

親の介護費用は平均500万円以上と言われています。 実際、生命保険文化センターの2022年の調査によると、介護にかかった費用の平均総額は約543万円にものぼります(出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」)。 また、約30%の家庭では、介護費用が600万円を超えていたという結果もあり、長期化することでさらなる経済的負担が生じていることがわかります。
📘 やり取りの実例:私の知人(40代主婦)は、父親の認知症が進行し、施設に入所することになりました。 当初は月12万円の施設費に驚いたそうですが、入所前の準備費用(家具・衣類・手続き)でさらに20万円以上かかり、合計で予想以上の出費に。 このとき「もっと早く話し合っていれば…」と後悔したと話していました。
だからこそ、40代の今から「情報・お金・モノ」の備えをしておくことが、未来の自分を助けてくれるのです。 急な出費を抑えるだけでなく、精神的なゆとりも生まれます。
なぜ今準備が必要なのか?

介護は、ある日突然やってくるケースが多いです。 「親が転倒して入院 → 退院後から在宅介護がスタート」など、前兆なく始まることも。 実際に私の周りでも「お父さんが骨折して寝たきりに」といった話が急に飛び込んでくることも珍しくありません。これは他人事じゃないですよね。私の母も段差がない道を散歩してるだけで転んでしまい焦ったことがあります。
厚生労働省の調査によると、介護が始まったきっかけの第1位は「骨折・転倒」(約20%)であり、突発的な事故によるケースが多いのが現実です。つまり、「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちに介護が必要になるリスクが潜んでいるのです。
しかし、事前に知識や物の準備がないと…
- 「いくらかかるかわからず不安…」
- 「必要なものを急いで買いに走る」
- 「きょうだい間でトラブルになる」
などの問題が起きやすくなります。特に金銭面や役割分担において、事前に家族内で話し合いをしていないことが争いの原因になりやすいです。
また、40代は「教育費」や「住宅ローン」など出費が多い世代です。内閣府の家計調査によると、40代世帯の平均支出額は月30万円以上にのぼり、子育てや住宅費が重なる中、介護費用が加わると家計は一気に圧迫されます。
親の介護が重なると、家計への影響も大きくなるため、前もって準備しておくことが安心につながるのです。
さらに、介護の費用は思った以上にかさみます。 例えば在宅介護では、
- 介護ヘルパーの利用(1時間あたり2,000〜3,000円)
- デイサービス(1回5,000円〜7,000円程度)
- 介護用おむつや食事サポート用品(毎月1〜2万円)
施設介護になると、
- 月額10万円〜20万円が相場
- 入居時に一時金として数十万〜数百万円必要な場合も
また、介護が長引くほど家計への負担は重くなります。 加えて、介護を理由に離職やパート時間の減少が起きれば、収入減という二重のダメージにつながるのです。
今すぐ始められる3つの準備

① 介護費用の平均額と内訳を知る
親の介護費用は、以下が目安です。
| 介護のタイプ | 月額の平均費用 | 期間の平均 | 総額の目安 |
|---|---|---|---|
| 在宅介護 | 約5万円〜7万円 | 約4年〜5年 | 約300万円 |
| 施設介護 | 約12万円〜15万円 | 約4年〜5年 | 約700万円 |
加えて、住宅改修(手すりの設置、段差の解消など)に20万〜50万円、介護用具(ベッドや車いす)の購入・レンタルに毎月数千円〜1万円、さらに食事の補助費、医療費なども上乗せされます。 これらを知らずにいると、準備不足で突然の大出費になりがちです。
📘 リアルなエピソード :在宅介護を経験した40代の女性は、初年度にかかった費用が約120万円だったと話しています。 内訳は、介護ベッドの購入と設置費で約20万円、デイサービスの利用料が月額5万円、食事の工夫のための調理器具・宅配弁当が月1万円程度、それに加え介護用紙おむつ代が年間で8万円超。 また、介護が進むにつれて福祉用具の更新や訪問入浴サービスなどが必要となり、2年目以降はさらに年間30万円以上の増加があったそうです。
📘 準備のコツ
- 毎月の生活費+10,000円を“介護準備費”として別に積み立てる
- 家計簿アプリで積立を「見える化」すると継続しやすいです
- 家族内で費用分担についても事前に話し合っておくと安心です
💡 おすすめアイテム
親と一緒に「介護についてどうしたいか」を話し合って書き込めるノートなどを使ってみてはいかがでしょうか?ご自身でお気に入りのノートを見つけてみてもいいですね!
② 介護保険制度とサービスの仕組みを知る
介護保険制度は、65歳以上または40歳以上の特定疾病がある方が対象です。 サービス利用には「要介護認定」の申請が必要で、自治体の窓口や地域包括支援センターで手続きできます。
手続きの基本的な流れは以下の通りです:
- 地域包括支援センターに相談(電話や来所で可能)
- 要介護認定の申請(本人または家族が申請)
- 調査員による訪問調査(本人の生活状況などをチェック)
- 主治医の意見書提出
- 審査会による判定(要支援1〜2/要介護1〜5)
- 結果通知 → ケアマネージャーとサービス計画作成
📘 リアルなエピソード: 40代男性は、母親の物忘れが気になり、地域包括支援センターに電話で相談。 「一度、要介護認定を申請してみましょう」とアドバイスされ、訪問調査と医師の診断書を経て、要介護2と判定。 その後ケアマネージャーと話し合いながら、デイサービスと福祉用具のレンタルを組み合わせたプランがスタートしました。 相談からサービス利用開始まで約1ヶ月でしたが、「誰に何を聞けばいいのか明確だったので安心だった」と話していました。
使えるサービス例
- 訪問介護(ホームヘルパー)
- デイサービス(通所介護)
- ショートステイ(短期入所)
- 福祉用具レンタル(手すり、ベッド、車いす)
これらは自己負担1〜3割で利用可能。 制度を知らないと「もっと安く利用できたのに」というケースも。
📘 準備のコツ
- 地域包括支援センターで情報を集めておく(パンフレット入手)
- 親の保険証や医療情報をファイルでまとめておくと、申請時にスムーズ
💡 おすすめアイテム
介護情報整理用に 制度や手続きの情報をまとめておける専用ファイル。楽天で買える「介護書類整理ファイル」は書き込み式で便利にできています。ゴチャゴチャしてしまう書類はまとめて管理したいですね。
③ 必要な「介護グッズ」を早めにリストアップしておく
介護が始まると、すぐに必要になるアイテムが多数あります。 例えば、突然寝たきりになった場合、ベッド横にポータブルトイレが必要になることも。 それぞれのグッズには活用シーンがあり、選ぶポイントを押さえておくと失敗が少なくなります。
■ 代表的なアイテムと活用ポイント
- ポータブルトイレ: 室内でのトイレ移動が困難なときに活躍。消臭機能付きや、掃除がしやすい抗菌仕様のタイプがおすすめです。 高齢者が使いやすい高さや、座り心地のクッション性にも注目しましょう。
- 滑り止めマット: お風呂や玄関、トイレ前など転倒リスクの高い場所に敷くことで事故を未然に防ぎます。 水に強い素材で、洗えるタイプが清潔で便利です。
- 防水シーツ: 夜間の失禁や食事中のこぼし対策に便利。繰り返し洗えるタイプを選ぶと経済的です。 家庭用洗濯機で洗えるか、乾きやすい素材かを確認して選ぶとよいでしょう。
- 介護パジャマ: 前開き・マジックテープ式のパジャマは、介護する側・される側両方にとって負担が軽減されます。 寝たきりの方には背中側に縫い目がない「肌当たりがやさしい設計」もおすすめ。
📘 リアルなエピソード: 「実家に帰省中に母が体調を崩し、急遽紙おむつを買いに行く羽目に…」というケースも。事前に見本や試供品を集めておくのも安心です。 また、実際に使用する前にレビューや口コミで使用感を確認しておくと、後悔のない買い物につながります。
💡 おすすめアイテム
・【ポータブルトイレ(消臭付き)】
・【防水シーツ(洗えるタイプ)】
【介護パジャマ(前開きマジックテープ)】
まとめ

親の介護費用は平均500万円以上とも言われ、想像以上の出費になることも少なくありません。 でも、40代の今から「知る・備える・話す」ことを意識すれば、介護が必要になったとき慌てずに済みます。
今すべきことはこの3つ
- 情報収集(制度・費用・必要なもの)
- お金の備え(積み立てや保険の検討)
- グッズの準備(楽天などでチェック&お気に入り登録)
家族を守るのは、あなたのちょっとした準備です。 将来「やっておいてよかった」と思える日が来るように。 ぜひ今、小さな一歩を踏み出してみてください。
それが、あなた自身と家族の未来を明るく支えてくれるはずです。
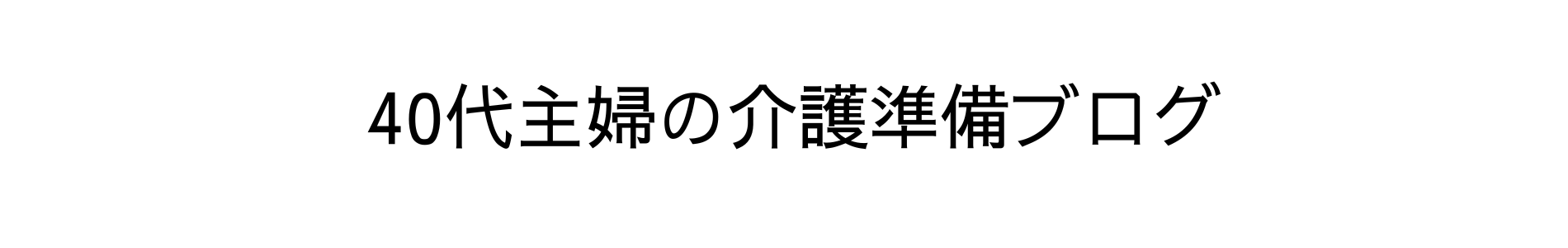




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46b6a0f3.af08e446.46b6a0f4.083156d5/?me_id=1365253&item_id=10000017&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnecoto-ohirune%2Fcabinet%2F06517971%2F06537875sku%2F1_flat.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


